|
CANNTAIREACHD
- MacCrimmori's Letter - No.10
|
|
David Naill のエレクトロニック・パイプ1st Sepember 1993 このところのポンド安につられて、とうとうあのエレクトロニック・パイプを買ってしまいました。
Piping Timesに広告が出ているDavid Naill & Co.の "EL2"
というタイプのものです。 ところで、本当のところ生粋のバグパイプ原理主義者である私は、エレクトロニック・パイプなんてものは、ゴアテックスのパイプ
バッグと同じく、伝統楽器における近代的技術のお遊びという位置づけで、あくまでも邪道の産物と考えていました。ですから、私が購入を決めたのは、このようなポンド安の状況によるところが大でして、もしポンド
がもっと高かったら、こんな《おも
ちゃ》に£249も出すのは気が引けたところでした。だって、これだ
けのお金(ポンド)をだせばちゃんとした《本物の楽器》が買える訳ですか
ら。ポンドの価値は同じなのは分かっているのですが、実際に財布からだす
《円》の軽さに思わず手が出てしまったというところです。 さて、注文してから待つこと3週間余り、エレクトロニック・パイプが手元に届きました。ところが、
本物を手にしてみてびっくり! それまで、このエレクトロニック・パイプなるものを《おもちゃ》だと決めつけていた
私の考えは、嬉しくも完全に覆されてしまいました。
「かっちりした感触のタンブラース イッチでチャンターの音色を選んでカチッ!とスイッチを入れ(チャンターの音色はハイランド・パイプとスモール パイプを選ぶことができます)、High-Aの音に合わせてチューニング。グリーンのランプの点滅がおさまった ところでチューニング完了。おもむろにドローンのスイッチを入れる。ブーンというドローンノートをバックにチャ ンターが唄い始める…。」 この一連の動作は、何故か、子供のころ憧れていたジャガーEタイプやトライアンフ
TR4といった60年代のブリティッシュ・スポーツカーを操る情景と相通じるものがあるように思えます。 「ブリティッシュグリーンのボディカラー。コノリー レザーの薫る品の良いシート。タンブラースイッチがずらり並んだ黒の結晶塗装のコンソール。ウォールナット製の磨き 込まれたステアリングホイール。短いストロークで小気味よくカチッ!と決まるシフトノブ。オープンにした運転席でエ キゾーストノートにまみれながら、緑濃いイングランドのカントリーロードを、生け垣すれすれに飛ばしていく。これぞ ブリティッシュ…!」
しかし、本当はこのような雰囲気ばかりでなく、楽器としての機能が最も重要なのは言うまでもありま せん。実のところ、このような外見の完成度の高さを見た後でも、私は楽器としての機能についてはまだ半信半疑でし た。つまり、ハイランド・パイプの演奏で一番避けなければならない「クロージングノイズ」(※注)の発生に関して、電気的な接点と指の接触を感知して音を出すシステ ムであるこの楽器がどの程度正確に反応するかということについて、期待をしながらも疑ってかかっていたというのが正 直な気持ちでした。 ところが、嬉しいことにこの疑いは完全に裏切られました。電極を押さえる指に応じて発せられる音の
フィールは、本物のプラクティスチャンターのそれとほとんど変わりません。いや、考えてみれば当然なのかもしれませ
んが、ある意味では本物よりも正直だともいえます。少しでも指がずれていれば正確に反応し、クロージングノイズも
はっきり聴こえます。Birl(バー
ル)やCrunruath(クルンルアー)といった込み入った装飾音
を始めとして、全ての装飾音がまさに小気味よく決まる、素晴らしいフィールを持っているのです。そして、ブラック
ウッドの手触りと相まって、本物のバグパイプのチャンターを演奏するような楽しみを味わうことのできる、素晴らしい
楽器だといえます。 正直なところ、本物のハイランド・パイプで音まみれになりながら、あるピーブロックを通して演奏す
るということは、リードの調整やドローンのチューニングといったことを除いて、単純にチャンターでのメロディーの演
奏と言ったことに限ったとしても、そんなに簡単なことではありません。 一方、プラクティスチャンターでいくら雰囲気をだして演奏しようとしても、息継ぎをしなくてはなら
ないし、すぐに息苦しくなってしまい、バグパイプらしい音楽を楽しむどころではありません。息継ぎに関して言えば、
あの Thomas
Pearstonがしたように、鼻から息を吸いながら吹き続けるという方法がないわけではないのですが、その技を修得することは、それこそ簡単なことでは
ありません。(それにしても、10年前のあの時、彼が私たちの目の前で8分50秒の "MacCrimmon's Sweetheart" を息継ぎせずに一気に吹き通したあのシーンは忘れられません) これらの様々な要因を考えたとき、このDavid
Naillのエレクトロニック・パイプは、ドローンの音にまみれながらバグパイプを演奏する喜びを、プラクティスチャンターのフィールを味わいながら室内
で手軽に楽しむ手段として、理想的なものだと思います。まして、スピーカーを使わずにヘッドフォーンを使えば、隣で
本を読んでいる奥さんに遠慮することなく、いつでもどこでも好きなだけ、自分だけのピーブロックの世界に没頭するこ
とができるのですから。 ところで、この David Naill &
Co.というパイプメーカーはどういう訳かその拠点をスコットランドではなく、南イングランド Somerset州のMinehead という土地に置いてます。地図で見るとブリストル海峡に面した海岸の保養地(避寒地)といった場
所のようです。もちろん私は行ったことはありませんが、今回エレクトロニック・パイプの包装に使われていた
“Somerset Free
Press”というローカル新聞を通じてこの地方の様子がうかがえてなかなか興味深かったです。 YoshifumicK Og MacCrimmori
|
|
|
|| Japanese
Index || Theme
Index ||
|
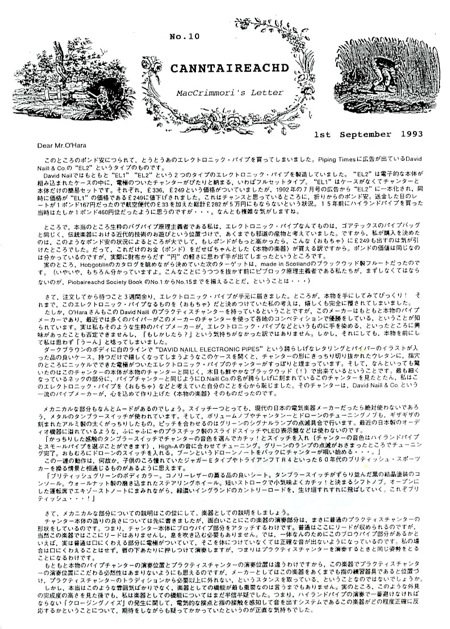

 ダー
クブラウンのボディに白のラインで
"DAVID NAILL ELECTRONIC PIPES" と
いう誇らしげなレタリングとパイパーのイラストが入った品の良いケース。持つだけで嬉しくなってしまうようなこの
ケースを開くと、チャンターの形にきっちり切り抜かれたウレタンに、指穴のところにニッケルでできた電極がついたエ
レクトロニック・パイプのチャンターがすっぽりと埋まっています。そして、なんといっても驚いたのはこのチャンター
の本体が本物のチャンターと同じく、木目も鮮やかなブラックウッド(!)で出来ているということです。最も細くなっ
ているネックの部分に、パイプチャンターと同じようにD.Naill
Co.の名が誇らしげに刻まれているこのチャンターを見たとたん、私はこのエレクトロニック・パイプを《おもちゃ》などと考えていた自分のことを心から恥
じました。そのチャンターは、
David Naill &
Co.という一流のパイプメーカーが、心を込めて作り上げた《本物の楽器》そのものだったのです。
ダー
クブラウンのボディに白のラインで
"DAVID NAILL ELECTRONIC PIPES" と
いう誇らしげなレタリングとパイパーのイラストが入った品の良いケース。持つだけで嬉しくなってしまうようなこの
ケースを開くと、チャンターの形にきっちり切り抜かれたウレタンに、指穴のところにニッケルでできた電極がついたエ
レクトロニック・パイプのチャンターがすっぽりと埋まっています。そして、なんといっても驚いたのはこのチャンター
の本体が本物のチャンターと同じく、木目も鮮やかなブラックウッド(!)で出来ているということです。最も細くなっ
ているネックの部分に、パイプチャンターと同じようにD.Naill
Co.の名が誇らしげに刻まれているこのチャンターを見たとたん、私はこのエレクトロニック・パイプを《おもちゃ》などと考えていた自分のことを心から恥
じました。そのチャンターは、
David Naill &
Co.という一流のパイプメーカーが、心を込めて作り上げた《本物の楽器》そのものだったのです。 メカ
ニカルな部分もなんとムードがあるのでしょう。スイッチ一つとっても、現代の日本の電気楽器メーカーだったら絶対使
わないであろう、メタルのタンブラースイッチが使われています。そして、ボリュームノブやチャンタンーとドローンの
チューニングノブも、ギザギザの刻まれたアルミ製の太くがっちりしたもの。ピッチを合わせるのはグリーンのシグナル
ランプの点滅具合で行います。最近の日本製のオーディオ機器に溢れているような、ふにゃふにゃのプラスチック製のス
ライドスイッチやLED表示盤などは使わないのです。
メカ
ニカルな部分もなんとムードがあるのでしょう。スイッチ一つとっても、現代の日本の電気楽器メーカーだったら絶対使
わないであろう、メタルのタンブラースイッチが使われています。そして、ボリュームノブやチャンタンーとドローンの
チューニングノブも、ギザギザの刻まれたアルミ製の太くがっちりしたもの。ピッチを合わせるのはグリーンのシグナル
ランプの点滅具合で行います。最近の日本製のオーディオ機器に溢れているような、ふにゃふにゃのプラスチック製のス
ライドスイッチやLED表示盤などは使わないのです。 さ
て、メカニカルな部分についての説明はこの位にして、楽器としての説明をしましょう。
さ
て、メカニカルな部分についての説明はこの位にして、楽器としての説明をしましょう。