第27話(2007/3)
"The Sister's Lament" を古(いにしえ)の表現で
知人や友人を失うことは、ある人にとって大きな悲しみ
ですが、やはり、いつの世でも血を分けた肉親を失うことの悲しみに勝るものはありません。
ピーブロックのテーマとして大きな割合を占めているラメント( Lament
)についても、お抱えパイパーが雇い主の依頼に応じて、自分とは直接は血縁関係の無い「誰それ」のために作ったラメント
よりも、パイパーが自分の身内を
失った悲しみを癒すために作ったラメントの方が、心打つことが多いのはごく当然のことでしょう。
ですから、"Lament for the Children"
"Lament for Alan, My son" "His Father's Lament for
Donald MacKenzie" "The Daughter's Lament" といった
ように、直接的に家族の喪失をタイトルにしたような曲は、そのタイトルだけでも何かグッと胸に迫りくるものがあります。
そして、そのような曲を聴く上では、その背景となった個々の家族喪失のストーリーを知ることによって、さらにその思い
は強くなり、その曲に対する共感の気持ちも高まります。
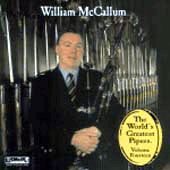 今をときめく、William
McCullum の World
Greatest Pipers シリーズ Vol.14のアルバムには2曲のピーブロックが収めら
れていますが、その内の1曲が正に肉親の喪失をテーマにしたと思われる "The
Sister's Lament(Cumha na Peathar)" というタイトルの曲で
す。
今をときめく、William
McCullum の World
Greatest Pipers シリーズ Vol.14のアルバムには2曲のピーブロックが収めら
れていますが、その内の1曲が正に肉親の喪失をテーマにしたと思われる "The
Sister's Lament(Cumha na Peathar)" というタイトルの曲で
す。
パイパー森はこのアルバムを入手して初めてこの曲を聴いた時から、何か強く惹かれるものがありました。
それは、私だけでなく他にもその様な人は居る様です。ボブさんのピーブロック・フォー
ラムに次の様な書き込みがありました。
"There's a good deal of
piobaireachd that brings tears to my eyes or makes my
hair stand on end, especially when played by a decent
musician. Hearing "The Sister's Lament" played by
William McCallum, for example, is utterly
heartwrenching."(words by
Michael23 from Bob Dunsire's Piobaireachd forum)
そこで、曲の背 景を知るために、A.J. Haddow の
"The History and Structure of Ceol Mor" を紐解いてみ
ると、やはり、なんとも悲惨 なストーリーが浮かび上がってきました。
時 は1661年、MacDonald of Keppoch というクランの第12代チーフ Norman の死去に伴い、大陸(フランスあるいはローマという説)で教育を受けていた2人の息子たちが帰国し、兄の Alasdair が第13代としてチーフの地位を継承しました。
大陸で見聞を
広めてきたこの若きチーフは、父から引き継いだ自分のクランの古いシステムを改革しようと試みました。しかし、いつ
の時代も、そして、どこの国や組織でも
同じ様に、このような改革を進めようとすると、旧体制を守ろうとする保守的な長老たちとの軋轢は絶対に避けて通る訳
にはいきません。様々な局面でのいくつ かの対立の末、旧体制派はとうとうこの若い兄弟を抹殺することを企てます。
そして、運命の1663年9月25日の朝(うぇ〜ん、パイパー森の誕生日じゃないか〜。そういえば、レッド・
ツェッペリンのジョン・ボーナムが泥酔して
眠ったままゲロを喉に詰まらせて窒息死したのも1980年のこの日だったよな〜)、まずは、暗殺者の刃は僅か16才
の弟 Ronald
の身体を貫きます。そして、弟を助けようとした若きチーフも同様に残忍な暗殺者の刃の餌食となってしまったという訳
です。
旧体制派と兄弟との対立を傍で見ていた兄弟の妹(単に
sister
なので、姉かもしれないですが、何となく妹と思っていた方がロマンチックではないでしょうか?)は、このような惨劇
が起こるであろうことを予見して、たま たま他の場所に居たこのクランの著名な吟遊詩人であった Iain Lom
という人のところに相談に出掛けていました(何故、相談相手が吟遊詩人なんでしょう?)。相談を終えて城に戻ったと
ころで、恐れていたとおりに兄弟が惨殺 されてしまった事を知ります。
妹は兄弟が殺されていた部屋に入った時に目にしたこと、そして、兄弟たちの死に至る物語を克明に描写した72節に
もなる哀歌を歌い上げたのでした。
それが、このピーブロックの基となった哀歌だと言い伝えられているのです。
実は、この後さらに、この兄弟の暗殺者たちに対するリベンジの顛末(先ほどの吟遊詩人 Iain Lom も登場)について、まるで映画「ブレイブハート」さながらの血なまぐさいストーリーがまだまだ続き、それはそれでとても 興味深い内容なのですが、ここでは とりあえず割愛しておきましょう。興味の有る方は、ぜひ、Haddow の本をご参照下さい。
さて、次にこの曲の構成について見てみましょう。
この曲は、例えば "Duncan MacRae of Kintail's Lament"(John Burgess の "The Art of the Highland Bagpipe Vol.2/Topic 1977" で名演奏が聴けます。)や "The Old Woman's Lalluby" などと同様に、バリエイションはウルラールを ほんの僅かづつ変化させて繰り返す形式で、最後まで Taorluath や Crunluath といった派手な盛り上がりはありません。
でも、なんていうのでしょうか、何とも言えないそのしんみりとした雰囲気は他にはちょっと比類すべきものがありません。他 の曲とは明らかに異なった独特の雰囲気があり、ユニークかつ孤高の曲だと思います。
特に、ウルラールの最終ラインの3小節目、E-D E-F と来た後の後半の D-B D-E の頭の D に HiG-F-E のランダウン (run-down) の3連譜装飾音が付く所が何ともググ〜ッと来る表現で、この特徴的な節回しは一度聴いたらどうしても耳から離れません。
"Lament for Patick Og MacCrimmon" に於けるあの "lowG から highG への the throws to G(Embari)" もそうですが、ピーブロックを聴いていると時々このよう一度で耳 に焼き付いてしまう印象的な節回しに出会う事があります。そして、そのような節回しに出会うと、なんとかしてその節回しを自 ら奏でてみたくなるのです。
…で、早速 Kilberry Book を開いてなぞってみたのですが…?????
The Sister's Lament -
C.Campbell setting /
Part.1& Part.2


(click the score to
enlarge/score by bugpiper さん)
どうも違うんです。よくある微妙な解釈の違いを超えてあちこちかなり違っている。まして、肝心のランダウンが表記さ
れていない…。
もちろん、直ぐに Piobaireachd Society Book も見たのですが、こちらも同様でした。実は両方ともタイトル下のクレジットに "From Colin Campbell's Canntaireachd" と記されているとおり、ソースは同じキャンベル・カンタラックなのです。
 この曲のもう一つの音源として、Andrew
Wright の "The Harmonic
Piobaireachd" というアルバムに収められているものがありますが、こちらは正に
Kilberry Book や Society Book(つまり、Campbell's
Canntaireachd)のバージョンでした。
この曲のもう一つの音源として、Andrew
Wright の "The Harmonic
Piobaireachd" というアルバムに収められているものがありますが、こちらは正に
Kilberry Book や Society Book(つまり、Campbell's
Canntaireachd)のバージョンでした。
でも、その演奏を聴いてもどういう訳か William McCallum の演奏(セッティ ング、スタイル?)程には心が動かされません。演奏の違いで曲の印象ってこんなにまで異なるものなのか?
 そんな思いのまま、ここ何年か
悶々 とし ながら過ごしていたのですが、先日、ついに McCallum
の演奏の元となっていると思われる楽譜を見つけました。2006年暮れに The Piobaireachd
Society からリリースされた、Roderick Cannon
の最新研究成果 "Donald MacDonald's
Collection of Piobaireachd Vol.1(1820)" にその楽譜が
有りました。
そんな思いのまま、ここ何年か
悶々 とし ながら過ごしていたのですが、先日、ついに McCallum
の演奏の元となっていると思われる楽譜を見つけました。2006年暮れに The Piobaireachd
Society からリリースされた、Roderick Cannon
の最新研究成果 "Donald MacDonald's
Collection of Piobaireachd Vol.1(1820)" にその楽譜が
有りました。
Kilberry Book
のイントロダクションで詳しく解説されていますが、18世紀後半から19世紀前半にかけて、それまで口承でしか伝えられ
て来なかったピーブロックを、五線
紙を使って表現し紙に書き残す、あるいは印刷物として出版する、といったことが行なわれる様になりました。そして、その
ような貴重な手書き楽譜集や出版さ れた楽譜集がいくつか現代に伝えられています。
中でも、19世紀前半に出版された楽譜集として最も貴重な存在が1820年に出版された Donald MacDonald による楽譜集(正確には "Donald MacDonald's Ancient Martial
Music of Caledonia" )と、1838年に出版された Angus MacKay の楽譜集("Angus
MacKay's Collection of Ancient Piobaireachd")で
す。
The Piobaireachd Society では(というか Roderick Cannon は)、これまでも、1760年に書かれた Joseph MacDonald の "The Compleat Theory of the Scots Highland Bagpipe" を、長年の研究に 基づく詳細な解説付きの復刻版としてリリースするなど、ピーブロックに関する貴重な書物を解析し た上で現代に伝えるといった作業を地道に行なっていますが、その最新の成果がこの"Donald MacDonald' s Book" なので す。
パイパー森はこの本をお正月休みの読み物にしようと、2006年12月に入手していました。ところが、"Patrick Og" や "Morar's" などといったお馴染みの曲が25曲も掲載 されている楽譜部分を目にしてワクワクしながらも、そこに到達する前に、例によって偏執狂的に詳細な Roderick Cannon の解説部分をなかなか読破でき ず、また、一応目を通した部分も十分に理解できたとはとても言い難いところなので、いつまでたってもこのサイトで紹介で きずにいたのです。
ただ、序文に書いてあるこの本の位置づけに関する説明によると、どうやら、Donald MacDonald の書き残したものは「ハイランド・パイプの音楽を現代的な手法(楽譜)で書きおろす」という分野における真の先駆者の成 果として高く評価されてはいます が、その表記方法や演奏スタイルの多くは現在では殆ど使われなくなってしまい、後世のさまざまな楽譜集に直接的に影響を 与え、現在流布している一般的な ピーブロックの楽譜表記のベースとなった Angus MacKay の書き残したものとは対照的な位置づけになっている、ということだそうです。
 話はそれてしまいますが、この序文の
解説 によると、Donald MacDonald と
同世代 に活躍していた Angus MacArthurもまた、同様にAngus
MacKayの流派との覇権争いに破れて(?)現代では消滅してしまったピーブロックの表現スタイルを伝える貴重な資料を残した存在であるということで
す。
話はそれてしまいますが、この序文の
解説 によると、Donald MacDonald と
同世代 に活躍していた Angus MacArthurもまた、同様にAngus
MacKayの流派との覇権争いに破れて(?)現代では消滅してしまったピーブロックの表現スタイルを伝える貴重な資料を残した存在であるということで
す。
2001年に、Roderick Cannon と Andrew Wright の協力を得ながら Frans
Buisman によって "The MacArthur -
MacGregor Manuscript of Piobaireachd(1820)" (マッ
カーサーとマクレガーの手書き楽譜)が詳細な解説文付きで出版されました。そもそもこの楽譜集は
1820年に出版が予定されていたので、実に200年近く経過して実現したことになります。
出版当時、かなり大きな話題になったので、パイパー森はもちろんこの本も直ぐに手に入れましたが、正直なところ Donald MacDonald's Book よりもさらに
難解だったので、やはり最後までは到底読破できずにいました。(⇒ デジタル化について)
ちなみに、これらの "Donald MacDonald's Ancient Martial Music of Caledonia" や "Angus MacKay's Collection of Ancient Piobaireachd " などは、今では全て The Piobaireachd Society や Ceol Sean のサイトの中にオリジナル譜面がアップされていますので、自由に閲覧やダウンロードすることが可能です。
実際に目にして頂ければ分かると思いますが、確かに Kilberry Book や Society Book では馴染みの無いような装飾音の使い方、そして、同じ装飾音でも表現の仕方が少し異なる例などがゾロゾロ出て来くるので ちょっと困惑されるかもしれませ。 でも、これが今では殆ど顧みられなくなってしまった古(い にしえ)のスタ イルだと思うとどこか感慨深いものがあります。
さて、この楽譜を手元に置き、例によって片方の耳で William
McCallum の演奏を聞きながら technopipes
のドローンをバッチリ調律して一緒に演奏してみると…。
いや〜、もう最高です。ランダウンで泣けます。
そして、何度か演奏を重ねるうちに、この曲は、"Children
" や "Patrick Og" と
はまた違った意味で very best なラメントではないか?という思いを抱く様になりました。
昨年夏にスコットランドに行かれた bugpiper さんからお土産として頂戴した "Legendary and Historical Note on Ceol Mor"(Compiled by Roy Gunn/2004) という小冊子にはこ の曲について次のように書かれています。
"Many people are of the opinion that this is among the finest laments we have."
そして、さらに William McCallum 自
身も古(いにしえ)のスタイルで演奏するこの曲について、正にそのように
考えているようです。
2003年6月の Bob さんのピーブロック・フォーラムで、叔父であり師匠である Hugh
McCallum が1986年にス
ターリングのあるお城でこの曲を演奏した際の印象について次の様に書いています。
"I like the idea of experimenting with other settings than those printed in PS/Kilberry (particularly like some of Donald MacDonald settings and timings of tunes). I heard Hugh MacCallum play Angus MacKay's setting of the Sister's Lament in 1986 at Airthrey Castle in Stirling and it remains the most brilliant piece of pipe music I have ever heard. " (William McCallum)
さて、数有るピーブロックの中でこの曲が際立って珍しいと感じられる点は「 Urlar よりもVar.1 の方が音符の数が少ない」こ とです。曲が進行するに従って楽譜が段々スカスカになっていくピーブロックなんて他にはちょっと思い当たりません。逆に 言えば、この二つを前後入れ替えた としても全く違和感が感じられない。ですから、この曲の場合 Urlar と Var.1 は一体として Urlar・Part.1&Part.2と考えた方がいいでしょう。(Society Book では、実際に Urlar と Urlar Doubling と表記されています。)
そして、本当の意味でのバリエイションは Var.2 からで、 Var.2 と Var.3 は
Singling と Doubling という関係。実際、Donald
MacDonaldの楽譜では、文字通り Var.2 と Var.2 Doubling
と記されています。(Society Book では、Var.1 と Var.1 Doubling と表記。)
そして、このダブル・ウルラールから発展する Var.2 Singling〜Doubling
のメロディーラインはなんとも印象的でグッと来ますね。Sumasu MacNeill は "Patrick Og" の Var.1
Singling〜Doubling を「全てのピーブロックの中で最高
のバリエイション・ライン」と書いていますが、このバ
リエイションはそれに勝るとも劣らない美しいメロディーではなのではないでしょうか。演奏していると
ゾクゾク来ます。
Var.3 (Kilberry Book では Var.4)は、いわゆる、Dithis を思わせる長短の音符が均等に並ぶバリエイションですが、その実、一般的な Dithis とは全く違うパターンで展開する、他では見た事も無い不思議なバリエイションです。そして、言うまでもなく実に美しい。 他の曲だったら「バリエイションがやっと佳境に入って来た」ってところでしょうが、この曲では何の未練も無くこれだけで あっさりとウルラールに戻ってしまう。
なんとも、潔(い さぎよ)い曲だと思います。
しかし、パイプのかおり第22話の ■ 本当に難し いピーブロックとは ■ の項にも書きましたが、実は Taorluath や Crunluath といった込み入った装飾音が出て来ないこのようなごく単純な構成の曲ほど、真にニュアンス豊かに表現するのは難しいものです。ですから、人によってはこの 曲を「込み入った装飾音が出て来ない」という理由で初心者向けのお勧め曲とする人がいますが、私は決してそうは思いませ ん。


 ま た、
Taorluath や Crunluath が出て来ないとはいっても、実は例えば Var.2
Doubling(Kilberry Book では Var.3)で繰り返し出て来るこの
D-LowG-E-LowG-D の装飾音は実はそれら以上に、奇麗に表現するのが難しい装飾音です。
ま た、
Taorluath や Crunluath が出て来ないとはいっても、実は例えば Var.2
Doubling(Kilberry Book では Var.3)で繰り返し出て来るこの
D-LowG-E-LowG-D の装飾音は実はそれら以上に、奇麗に表現するのが難しい装飾音です。
(中央は Kilberry Book の省略表記、右端がその演奏方法の説明)
ちなみに、この装飾音は、Kilberry Book の曲の中でもごく少数の曲でしか出てきません。パイパー森のレパートリーの中では "Lament for the Chldren" の Var.3 に6回出て来るのですが、正直に白状するとこの装飾音だけはいつまでたっても歯切れ良く演奏できなくて、いつも歯がゆい思いをしています。
さて、今回の記事に C.Campbell Ver. と D.MacDonald Ver. の楽譜を作成・提供して下さった bugpiper さんは、なんとさらにこの両方の楽譜を一度に見比べられるように、一行毎にそれぞれを交互に並べた楽譜を書き上げられま した。こんな力作、他には絶対に見 られません。ぜひ皆さんもこの恩恵をご享受下さい。※ 例によって、それぞれの楽譜から大 きなファイルにリンクしています。
"The Sister's Lament - Cumha na Peathar"
C.Campbell setting vs.
D.MacDonald setting / Part.1& Part.2


(click the score to
enlarge/score by bugpiper さん)
上段/黒色=C.Campbell setting vs. 下段/
青色=D.MacDonald setting
The score in black is C.Campbell setting vs. The score in blue is D.MacDonald
setting
All scores in this page by courtesy of
"bugpiper". Copyright
(C) 2007〜 "bugpiper" All Rights Reserved
⇒ 後日談
⇒
Donald MacDonald's Book & MS/MacArthur-MacGregor
MS デジタル版
【2018年
9月追記】
 1988年9月号 "Piping Times" の中で紹介したよう
に、YouTube にアップされている 2015年 The Donald MacDonald Quaich
の動画の一つとして、Niall
Stuart によるこの曲の Donald
MacDonald のセッティングに忠実な演奏を観る事ができます。
1988年9月号 "Piping Times" の中で紹介したよう
に、YouTube にアップされている 2015年 The Donald MacDonald Quaich
の動画の一つとして、Niall
Stuart によるこの曲の Donald
MacDonald のセッティングに忠実な演奏を観る事ができます。
そこでも触れたように、この演奏を聴いてみると、William
McCullum の演奏は基本的には Campbell のセッティングであり(特にウルラールに於けるタイミン
グの取り方)、そこここに MacDonald
セッティングの表現を(不規則に)取り入れたもの。ある意味、少々中途半端なものだという事が分かってき
ました。
Donald MacDonald のセッティングでは、William McCullum の
演奏の中で私が最初にグッと来たウルラールの最終ラインのランダウンに限らず、そこここに三連符の装飾音が多用されてい
ます。三連符の装飾音はこの曲に限らず Donald MacDonald のセッティングの大きな特徴の一つです。
最初に聴いた時はこれらの三連符装飾音は少々「装飾
過多」の様に思えたのですが、何度も聴き込んで馴染んでくるに従い、この表現が極めて魅力的に感じられる様になりまし
た。また、ウルラールに於ける長短のタイミ ングの取り方は明らかに MacDonald セッティングの方が理にかなっている様
に感じられます。
その様な訳で、Niall Stuart の演奏に出会って以降、私も Donald MacDonald のセッティングに忠実な演奏の練習に切り替えました。そして、以前にも増してますますこの曲の魅力に惹きつけられる様に なりました。
